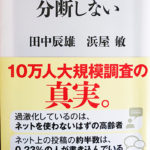ピカソの作品「ゲルニカ」は世界で最も有名な絵画のひとつでしょう。
1937年4月、スペイン内戦でフランコ反乱軍を支援するナチスドイツがスペインバスク地方の中心都市ゲルニカを無差別空爆。その惨状を主題にピカソが制作したことはあまりにも有名です。
パリ万博で公開された後、ゲルニカは、独裁者フランコが死去してスペインが民主制へ移行する1980年代まで、ニューヨーク近代美術館に保管され、スペインに帰ることはありませんでした。
この物語では、父の赴任先ニューヨークで幼いころに見たゲルニカに衝撃を受けた主人公・瑤子が、美術史を学びついにニューヨーク近代美術館にキュレーターとして勤務。マドリードで出会った夫イーサンと幸せに暮らしているとき、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件が発生し、愛する夫イーサンを失います。
アメリカはその後、アフガニスタンを空爆。さらにイラク戦争へ突入しようとするとき瑤子は、決意します。
いまやるべきピカソの展覧会は何か、ピカソがアートの力で、いかに不条理な武力行使と戦ったかということを検証する「ピカソの戦争」以外にない、と。
しかし、ゲルニカを借り出そうとする瑤子の取り組みは困難を極め、その間に、国連安保理ではイラクへの武力行使が決議され、バグダッド空爆がなされようとするとき、国連安保理議場ロビーで記者の囲み取材を受けるアメリカ国務長官の背後のゲルニカ・タペストリーには何と暗幕がかけられていた。これは一体誰の仕業なのか、そして門外不出の絵画ゲルニカは借り出せるのか、後半は、ゲルニカ奪還をめざすテロ組織「バスク祖国と自由」の参入も加わり、一挙にサスペンス仕立てとなって物語は進みます。
そしてついに実現した特別展「ピカソの戦争」。開催に当たって、館長がスピーチします。「ピカソいわく、芸術は、決して飾りではない。それは戦争やテロリズムや暴力と闘う武器なのだ、と。」
この本の著者・原田マハさんは、ゲルニカがアメリカで展示され続けていたニューヨーク近代美術館に、実際にキュレーター(美術館などで展覧会などを企画する権限と専門性を備える管理職学芸員)として勤務した経歴をもつ美術の専門家でもあります。
女性関係に揺れ動いていたピカソが、ゲルニカ空爆を機に、パリのアトリエで渾身の作品を制作する過程を、愛人で写真家のドラの目を通して描く部分を章ごとに織り込みながら、空爆へのピカソの怒りと、アメリカのイラク空爆を前に、絵画ゲルニカに込められた現代的な意味をも描いた作品となっています。
いままたトランプ大統領の過激で挑発的な言動と、北朝鮮の愚行が、朝鮮半島での戦争を想起させるという不穏な世界にあって、私たちもゲルニカにかけられた暗幕を取り払って、改めてピカソの描いた戦争の画面を見つめ直す必要がありそうです。